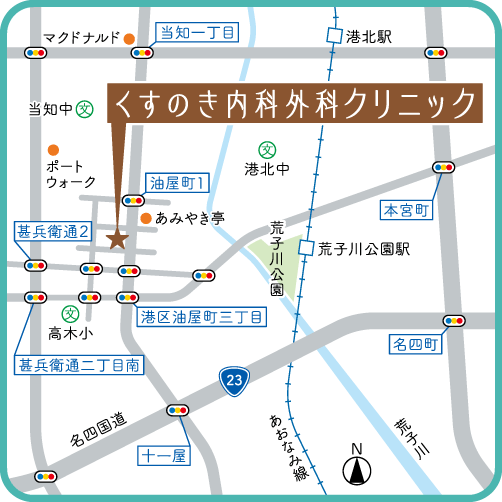肛門外科について

肛門外科は、肛門に関わる様々なトラブルに関し、外科手術などの治療を行う専門診療科です。各種の痔疾患を中心に、肛門周辺のかゆみや痛み、できもの、しこり、さらには排便トラブル等に関し、幅広く対応いたします。肛門の病気については、羞恥心から医療機関の受診をためらってしまう患者様もいらっしゃいます。しかし、早い段階で治療を行っておかないと、患部の状態が悪化してしまい、難しい治療が必要になったり、肛門機能に障害が残ったりしてしまうことがあります。
当院では、患者様のプライバシーに配慮しつつ、専門的な治療を行っています。痔は早期に治療を開始すれば、比較的治癒しやすい疾患です。また、これまで入院して手術が必要だった症例も、注射などの治療で、入院せずに治療できるように、医療も進歩してきました。お早めにご相談いただくことで、お悩みをより早く解決できるかもしれませんので、まずは一度、ご受診ください。
主な疾患
痔核(いぼ痔)
痔のなかで最も多いのが「痔核」です。一般的には「いぼ痔」と呼ばれることが多いです。この病気になると、肛門付近の血流が悪くなり、うっ血し、さらに静脈がこぶ状に拡張します。これに伴い、排便時に出血したり、肛門の周りが腫れてきたりします。発生する場所により、内痔核と外痔核に分けられます。
このうち内痔核は、ほとんど痛みを感じることなく進行します。しかし、進行して痔核が大きくなると、脱肛するようになります。脱出も初めのうちは指で押し込めば戻りますが、さらに進行すると戻らなくなり、痛みを伴うこともあります。 治療に関していうと、経口薬や注入軟膏、坐薬で対応することもありますが、硬化療法やゴム輪結紮法、手術療法が必要になることも多いです。
一方の外痔核は、激しい運動をしたり、急に重いものを持ったりした後などに突然血の塊が肛門にでき、腫れて痛みます。お薬で治癒することも多いのですが、痔核が大きくて痛みが強いケースでは、患部を切除する、あるいは血の塊を取り除く治療が必要になります。
ALTA療法について
痔の治療方法のひとつである硬化療法は、内痔核の患者様に適用されることが多いです。特に脱肛や出血の制御が難しい場合に効果的とされています。
ALTA療法では、1つの痔核に対し4ヵ所に注射を行い、施術は局所麻酔のもとで実施されます。施術後は、麻酔の影響が完全になくなるまで院内で安静にすることが求められます。
この治療に使用される薬剤には、硫酸アルミニウムカリウムやタンニン酸が含まれており、これらの成分によって痔核が硬化し、縮小する作用があります。ALTA療法の普及により、これまで手術が必要とされていた内痔核でも、この治療法のみで改善するケースが増加しているのが特徴です。
この治療により、痔核への血液の流入が減少します。その結果、脱肛の状態が軽減され、痔核そのものが縮小していきます。最終的には発生した部位に癒着して固定されるため、脱肛が消失します。
痔核の縮小には約1ヵ月程度の期間を要し、その間は定期的な通院が必要とされています。
この治療には副作用が現れる場合もあります。主な症状として、血圧の低下、頭痛、食欲不振、肛門部の違和感、さらには痔核周囲の粘膜が硬化することで排便が困難になることが挙げられます。
裂肛(切れ痔)
裂肛は、肛門上皮が切れている状態です。一般的には「切れ痔」と呼ばれています。便秘や下痢が続くと、肛門上皮が切れ、痛みや出血を伴うことがあります。なお、裂肛には急性裂肛と慢性裂肛があります。このうち急性裂肛は、排便時に痛みや出血を伴いますが、傷が浅いことが多く、ほとんどが数日で回復します。 これに対し、裂肛を繰り返して傷が深くなると、慢性裂肛になってしまい、痛みが持続します。患者様によっては、傷の内側に肛門ポリープができたり、外側が腫れ上がったりすることもあります。
痔瘻(あな痔)
痔瘻は、肛門の周りに膿が溜まる肛門周辺膿瘍が原因となって発症します。直腸と肛門の間にある歯状線という部分の肛門陰窩というくぼみの中で細菌感染が起き、化膿することで肛門周辺膿瘍となります。この段階では、激痛や発熱を伴います。肛門と皮膚の間に溜まった膿は、瘻管を作りながら進行し、やがて皮膚側に穴が開いて膿が排出されると症状は和らぎます。しかし、瘻管は残ってしまい、痔瘻になってしまうのです。この状態を放置していると、瘻管に再び便が入り込んで炎症を繰り返すようになります。さらに管が複雑に枝分かれして難治性の痔瘻となり、肛門機能に支障をきたす危険があります。そのため、手術による治療が必要になります。